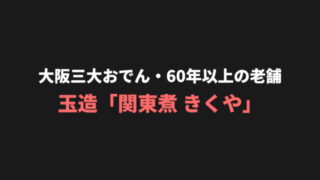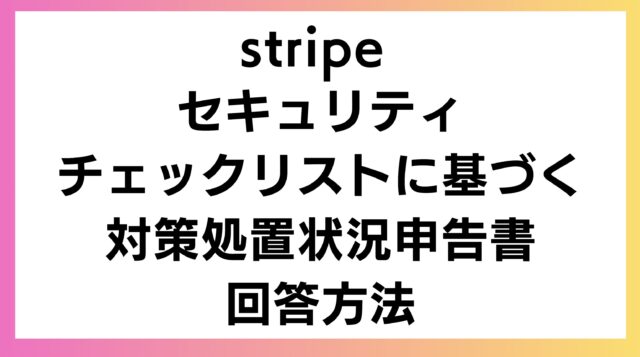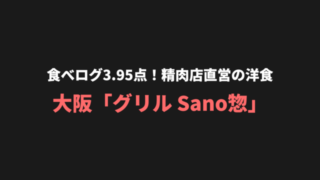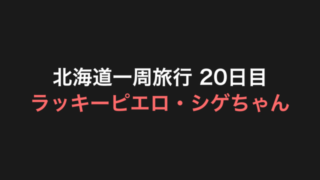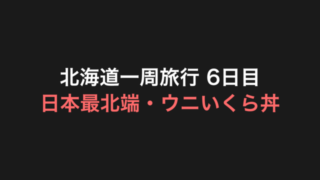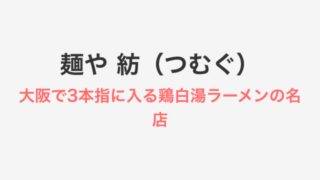小説「東京起業ストーリー」
第9話:遂に決断の時
「引き続き、宜しくお願いします!」
個別セッションの場所に決めたカフェの席を立つとき、木嶋夏帆はそう言って深々とお辞儀をした。
「いえ、そんな。もうそんなにかしこまらなくても大丈夫ですよ」
慌てて沙奈も立ち上がり、頭を下げる。三回目の面談もこれで無事に終わった。
木嶋夏帆は郊外にネイルサロンを構えて一年、売り上げが伸びずに苦心していたところ、沙奈のステップメールを見て連絡してきた。沙奈の新プログラムの最初のクライアントだ。
最初は引っ込み思案だった木嶋も、沙奈のアドバイスを受けて第一印象からどんどん変えていった。今では接客が明るくなり、新規客のリピート率が増え、嬉しい悲鳴を上げている。
しかしそれ以上に喜んでいたのは沙奈だ。もちろん木嶋の前では本人より喜ばないように努めてはいたが、内心はウキウキだった。この分ならもう大丈夫、沙奈は足取りも軽く帰路へ着く。
「ただいま~」
お帰りなさい、とフェアッキーが、続いてスザッキーが迎えてくれる。沙奈は木嶋のネイルサロンが好調であることを告げ、喜んだ。
「凄いじゃないか、沙奈。大成功だね!」
「ええ。篠田さんも中村さんも、こんな感じで行けばいいんだけど」
篠田も中村も、沙奈のクライアントだ。木嶋の面談後、立て続けに二人から連絡が入った。まだ色々試行錯誤している段階だが、二人ともすっかり沙奈と打ち解けている。
木嶋に許可を取り、ネイルサロンの売り上げが伸びていることをブログで告知し始めた。その成果だろうか、今週はさらに新規の面談予定が二件入っている。
「沙奈、こうやってどんどん告知していけば、もっともっと依頼が増えるよ!」
スザッキーはそう言って笑ったが、突然沙奈からふっと笑顔が消える。
「そう、ね」
沙奈はジャケットを脱ぎ、ダイニングを抜けて部屋へ入っていく。
フェアッキーの入れてくれた梅こぶ茶を飲みながら、沙奈は長い溜息をつく。以前はコーヒーや紅茶を好んで飲んでいたのだが、今ではすっかり梅こぶ茶のとりこだった。程よい酸っぱさが沙奈の心をほぐしていく。しかし頭に浮かぶのは仕事の事ばかりだ。
これから週末の面談の準備をしなくちゃ、それから篠田さんのエステサロンの新メニューを考えて、ええと、その資料はもう揃ってたんだっけ、矢継ぎ早にやることが浮かび出す。そんな折、突然机の上のスマホが鳴りだした。画面に表示された文字を見て、動きが止まる。
「沙奈、出ないの~?」
「……加藤部長からだ」
「えっ!?」
二人が驚く。沙奈は緊張しつつ電話に出た。
「はい、風見です」
「おう、元気か。今電話いいか?」
加藤の声は以前上司だった頃と同じように、自信に満ちていた。
「見てるぞ、ブログとメルマガ。凄いじゃないか、個人起業家に目を付けるとは恐れ入ったぞ」
「いえ、ありがとうございます」
「しかも売り上げ保障とはね、うちじゃ絶対真似できないシステムだ。正にお前にしか提供できないプログラムだな」
「そんな……、私はがむしゃらにやってるだけですから」
「ははは、謙虚なとこは相変わらずだな。それでだ、今回電話したのはだな」
沙奈は来た、と思った。あまり向こうのペースに乗せられたくはない。
「会社に戻れ、というお話ですね」
「うん。そうなんだがな、ただ戻ってこいと言うんじゃない。ネクストランクでは、この度お前、いや風見沙奈さんを、特別指導員として迎えたいんだ」
「特別指導員?」
「ああ、今度新設されたポジションだ。もちろんお前の、ああすまん、風見さんのために造られたんだぞ。業務内容は社内講師の指導、新規格の考案、社の営業方針の見直しだ。正に我が社の命運を握ることになる」
まさかそこまで、と沙奈は思った。新設にあたり社内で加藤が中心となったことは疑うべくも無かった。
「まあ俺も、こんな大事な話を電話で済ませる気は無いよ。今度食事でもどうだ? 俺はいつでもいい。空いてる日取りを教えてくれ」
まずい、これでは完全に向こうのペースだ。そう思ったがもう遅い。
「……連絡待ってるぞ、じゃあな」
短い電話だったが、加藤の目的は十分果たされた。沙奈がほとんど意見を言う間もなく切られた。
「……」
コトン、とテーブルの上にスマホを戻し、沙奈は放心する。
「沙奈ごめん、聞こえちゃった」
スザッキーが謝る。
「あ、ううん。それは全然いいの」
驚きのあまり、次の言葉が出てこない。そこで突然、
「やったじゃない、沙奈!」
フェアッキーが大声をあげて沙奈の胸に飛びつく。
「わっ」
「沙奈の頑張りが、こんな形で叶うなんて! 今会社に戻れば、前よりもっと沙奈のやりたいことが出来るわよ! おめでとう!」
フェアッキーは笑った瞳を向けてくる。それはこれまでとは違う、すべてを見通したような瞳だった。
「えっと、でも、困るっていうか」
「何言ってるの、沙奈! さっきもお茶を飲みながら、ちょっと悩んでたじゃない。そうよね、今の仕事が順調に行ったって、ずっとうまく行く保証は無いものね。それにどこまで一人でやれるか、不安だったんでしょ?」
沙奈はこれまで見たことのないようなフェアッキーの態度が怖くなる。
「ちょ……、あれ? どうしたのフェアッキー。いつもの優しいあなたじゃない」
「確かに、いつもより厳しく聞こえるのかもしれないわ。だって物凄いチャンスなのよ。ねぇ、戻りましょうよ。私はあなたのためを本当に思ってるのよ? 今戻れば前以上の待遇と安定がやってくる」
その言葉に、沙奈の胸はかぁっと熱くなる。
「私は、待遇や安定を求めて独立したんじゃないわ」
「でも最近、いつも辛そうよ? いえ、出会ったときからずっとかしら。考えてみて、五年後、一年後の未来だって想像出来る? 出来ないでしょ。今の仕事で一生、本当に生きていけるの?」
「そんなの、会社に戻ったって同じよ!」
「同じじゃない!」
沙奈の体はビクッと震える。最初に叫んだのは沙奈だが、それ以上の大きさでフェアッキーが被せてきた。
「沙奈、今のあなたがもし駄目になったら、誰があなたを救ってくれるの?」
沙奈は二人がいるじゃない、と言おうとして止まる。そうだ、私はどうして今まで考えてこなかったのだろう。あまりにも自然になりすぎていた。突然やってきた妖精が、突然いなくなったってなにも不思議ではない。沙奈はとっさに、すがるようにスザッキーを見る。
「……僕は何も言えない。自分で決めるんだよ、沙奈」
そう言ったスザッキーの顔は、これまでよりもずっと他人に見えた。いつも無邪気に笑ったり、冗談を言ったり、慌てたり、そして何より力強い言葉でアドバイスをくれた、優しい彼の姿はどこにもない。
「そんな……、いつもみたいに言ってよ、私を励まして。どうしたらいいのか教えてよ。フェアッキーも、いつもみたいに……」
沙奈の両目から涙がこぼれる。二人は沙奈の前に立ち、じっと表情のない瞳で見上げている。
「僕は沙奈の生き方までは決められない」
「私は沙奈の幸せを、心から願ってる」
沙奈は混乱し、言葉がまとまらない。二人に涙を見せるのは初めてだった。そういえば、もうずいぶん泣いていなかった。以前は時々どうしようもなく不安になり、自然と涙が頬を伝うこともあった。けれど、二人が来てからそれは無くなった。そこまで考えて、沙奈は寒気を感じた。また社会の中で、たった一人で生きていかねばならない。会社を辞めて初めて感じた不安、自分に吹きすさぶ冷たい風が、再び身も心も包み込んでくる恐怖に駆られた。
どれくらい泣いただろう。窓の外で夕日が赤々と燃えている。それは太陽が沈むとき、一日の最後に見せる激しいきらめきだった。赤い光と黒い影が、部屋の中を真っ二つに分けている。
「……私は」
しばらく無言だった。沙奈は指先を両目に当て、ぎゅっと絞って言った。もう涙は止まっている。
「私は自分の生き方に迷ってきたし、これからも迷い続けると思う。けれど確かなこともあるの。それは私が自分の信じるように生きるってこと。……未来は分からないし、どこかでまた道を変えるかもしれない。けどそれは今じゃないわ。私は、私を信じてくれる人たちのために頑張りたい。私の思う、私だけのやり方でね。だから会社には戻らない。今はこのまま、思うように走っていたいの」
沙奈の決意を聞いた二人の顔に、みるみる表情が戻る。それは次第に笑顔となり、沙奈の心を優しく触った。
「沙奈、立派だよ」
沙奈は頷く。
「よく言ったわ、沙奈……」
フェアッキーはそう言うと、ゆっくりと浮き上がる。と、急にピキピキとガラスにヒビが入るような音が聞こえてきた。
「えっ……、フェアッキー、仮面……」
沙奈の目の前で、フェアッキーの仮面にみるみる亀裂が入っていく。